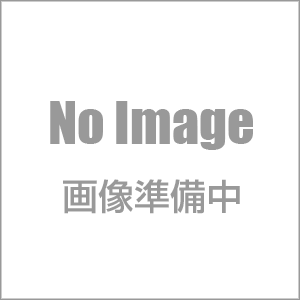プロダクトへのこだわり
CRAFTED QUALITY

THE CORE OF PRODUCT CREATION
プロダクトの根幹は「毎日飲めるか」
タンパク質は健康づくりに欠かせない栄養素。でも、現代の食生活では不足しがち。だからこそ、手軽に補えるプロテインの役割は大きい。
ULTORAが大切にしているのは、“毎日飲めるか”という視点。
そのために、飲み続けても安心な安全性、日常に取り入れやすい使いやすさ、そして飽きのこない美味しさを追求しました。
5つのこだわり

INGREDIENT
本質的な成分設計
たまにご褒美に食べるお菓子のような存在とは違い、毎日飲むものだからこそ。ULTORA基準で成分を選び抜き設計。
3つのフリー素材
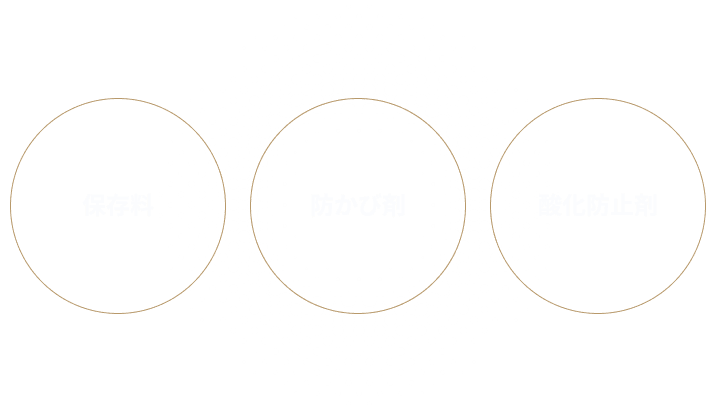
4つのポイント
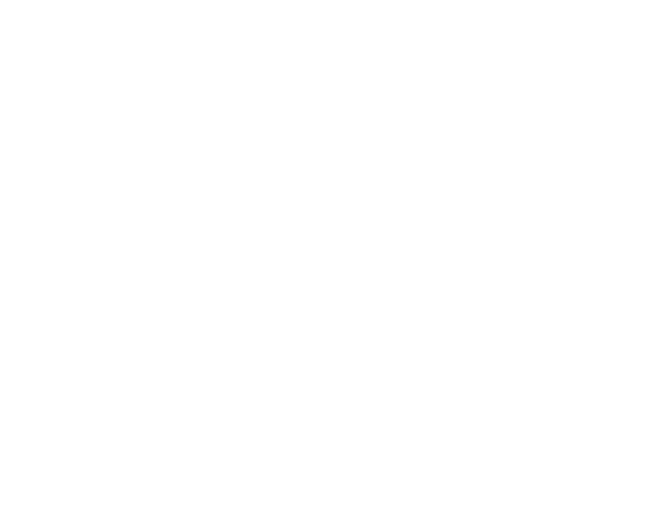
甘味料
選定基準
本質的
- 人間のカラダにとって適切な量/栄養素/種類
- サステナビリティ(持続可能性)を踏まえた配合
- 効果に対して明確なロジックがある
透明性
- 原材料の選定基準(=役割を明確に開示※自信を持ってブランドとして発信できるかが原材料の選定基準)
Professional
栄養分子学のほかに、提携衛生機関などテクノロジーの最適なバランスを追求し、各分野の研究者や専門家とも協力して研究・開発を行っています。

蜂屋雅司
分子栄養学の資格を複数有するプロアスリートコーチ

EASE OF USE
”粉っぽさ”や”溶けにくさ”を解消した成分配合
加工方法や乳化剤の調整など、細部までこだわり抜いた結果、価格・品質・使いやすさの理想的なバランスを実現しました。

DELICIOUSNESS
味の濃さとさっぱり感の絶妙なバランスの追求
口あたり、舌に乗った瞬間、そして後味——3つの味覚ポイントに分けて設計し、「しっかりした味わい」と「スッと消える後味」の両立を実現。原料ごとの風味の違いを見極めながら、何度も試作を重ねて完成させた、“濃厚なのに重くない”プロテインです。

PACKAGE
生活に自然と溶け込む”佇まい”
ULTORAは、プロテインをもっと身近な存在にするため、性別を問わずインテリアに馴染むよう、黒と白のマット素材を基調にデザイン。
人の体をイメージした逆Aラインのシルエットに、和色のアクセントを添え、機能美と感性を両立させたパッケージに仕上げました。あなたの日常に、さりげなく、美しく寄り添うプロテインです。

SAFETY
品質管理
「本質的な健康」を支える製品づくりのために、原材料から製造、出荷に至るまで徹底した品質・衛生・安全管理を実施しています。
品質管理への取り組み
独自の規格書様式で全原料の安全性を確認。法令・アレルゲン・農薬等のリスク管理を徹底。すべての原料に独自の規格書様式を適用し、アレルゲンや農薬残留、遺伝子組み換えの有無を含む安全性を確認。メーカーとの連携体制も構築し、法令準拠を徹底しています。
手順書に基づく製造と品質管理部の巡回で、工程の適正と継続的な改善を実施。衛生・工程管理の手順に基づき製造を行い、品質管理部がラインを巡回してチェック。定期的な設備検査や継続的な品質改善も実施しています。
作業服・除塵・エアーシャワー等で混入を防止。ふるい・マグネットも活用。専用の作業服・ネット・手袋・ゴーグル着用を義務づけ、入室時には除塵・手洗いを徹底。吸引式クリーナーやエアーシャワーの活用に加え、篩別機・除鉄マグネット等も導入しています。
二重扉や外部業者との連携で侵入を防ぎ、定期モニタリングを実施。作業場の出入口を二重構造とし、外部業者と連携して定期的に防虫・防鼠対策を実施。発生状況のモニタリングと報告会も毎月行っています。
全製品にX線・重量検査を行い、不良品を自動除去。製造中の全製品を対象にX線検査と重量検査を行い、異物や重量の異常を自動的に除去。出荷前の品質を確保しています。
味・香り・成分・微生物など多角的に検査。外部評価で検査精度も向上。官能検査(味・香り)、理化学検査(かさ比重・成分分析)、微生物検査を実施し、常に安定した高品質を維持。検査精度向上のため外部サーベイランスにも参加しています。
入場記録・監視カメラで工場内のセキュリティ体制を強化。工場敷地内は入場者を記録・監視し、監視カメラとモニターによるセキュリティ体制を構築。不正侵入や事故リスクの低減にも取り組んでいます。